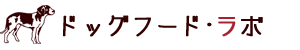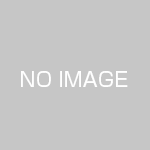犬の病気対策として、ドッグフードはとても重要です。
病気のワンちゃんは、症状によって栄養代謝にトラブルを抱えています。そのため、健康な犬のドッグフードとは違い、各病気に対応した食事療法が必要となります。
このページでは、犬の病気を9種にわけ、それぞれに適したドッグフード・食事療法の栄養条件をご案内します。
<目次>
1.犬の下痢嘔吐など、消化器疾患
下痢嘔吐をくり返すワンちゃんは、消化器に何らかのトラブルを抱えている可能性が高いです。消化器の病気はとても複雑で、はっきりとした病名がつかないこともよくあります。
だからと言って、下痢嘔吐を軽くみてはいけません。放っておくと、生命に関わる病気となることもあります。
もし、病名がつかなかったら、「胃」「小腸」「大腸」「膵臓」のどこに病巣があるのか、つきとめるようにしましょう。下痢嘔吐など症状をチェックすることにより、病巣の部位を推測することができます。
◇胃や小腸 → ユルユル、ピーピーな軟便・下痢嘔吐、食欲不振
◇大腸 → ドロッとした黒色の下痢・うんち、しばしば黒っぽい血便
◇膵臓 → 黄色の粘液便・下痢嘔吐、食欲不振
犬の胃の病気
胃炎・胃潰瘍など、胃にトラブルを抱えるワンちゃんは、消化しやすいドッグフードを与えます。胃への負担を和らげるためです。
消化しやすいドッグフードとは、炭水化物・タンパク質・脂肪、それぞれが消化吸収しやすいものを指します。消化しやすいことを専門的には、「消化率が高い」「高消化性」などと表現します。もし「消化率が高い」「高消化性」というドッグフードを見かけたら、犬の胃に配慮した条件の一つを満たしていると考えられます。
そして、消化しやすいことに加えて、少量でしっかり栄養補給できることが望ましいです。できるだけ、胃に負担をかけないように、少し食べるだけで十分なカロリー・炭水化物・タンパク質・脂肪が補えるドッグフードが理想です。
さらには、食物繊維の量が控えめであることもポイントになります。食物繊維は多い方が、犬の胃に優しいイメージがあるかもしれません。しかし、肉食性が強いワンちゃん達にとって、多すぎる食物繊維は、胃に負担を与えます。消化率を下げることにもつながるため、食物繊維は控えめが好ましいです。
ミネラルのバランスも重要です。胃を悪くしているワンちゃんは、嘔吐や下痢を伴います。それにより、水分とともに体内ミネラルが失われ、バランスを崩すことになります。脱水症状を防ぐために、バランスよくミネラルを補ってあげましょう。
まとめると、「高消化性」「高栄養」「控えめの食物繊維」「バランスよくミネラル補給」が「犬の胃の病気」に適したドッグフードの栄養条件です。
犬の小腸の病気
「小腸」に病気・トラブルを抱える犬も、基本的には「胃」の病気対策と同じような食事管理が必要です。つまり、「高消化性」「高栄養」「控えめの食物繊維」「バランスよくミネラル補給」というポイントが挙げられます。
ただし、状態によっては、次でご案内する「大腸」の病気・トラブル対策と同じ食事内容が好ましい場合もあります。
犬の大腸の病気
犬の「大腸」の病気対策は、「胃」「小腸」と食事内容が異なります。大きな違いは、「食物繊維が豊富なドッグフード」という点です。食物繊維が多い分、炭水化物・タンパク質・脂質は、それぞれやや少なめになります。それに応じて、カロリーも控えめです。
一方で、大腸系の病気を抱える犬だからといって、食物繊維量が多くなると、他の部分に負担がかかるケースもあり、注意が必要です。
また、食物繊維の種類やバランスも重要です。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスなどが留意ポイントになります。
犬の膵臓の病気
犬の「膵臓」の病気として、多いものは「膵炎」です。「膵炎」の食事対策については、高脂血・高血糖の病気として、次のテーマでご紹介します。ここでは、「膵炎」に次いで多くみられる犬の膵臓疾患として、「膵外分泌不全」の食事のことをご案内します。
膵外分泌不全とは、膵臓の消化酵素の分泌不足によりおこる犬の病気です。犬の消化不良の最も一般的な原因とされています。膵外分泌不全の犬の症状として、慢性的な下痢・食欲不振・消化不良・体重減少・発育不全などがみられます。
犬の膵外分泌不全では、「高消化性」「適量の脂肪(少なめ)」「低・食物繊維」の3点を満たすドッグフードが望まれます。また、犬の症状によっては、ビタミンE・ビタミンK・亜鉛・銅などが不足することもあり、これらの栄養を補足することも一つです。さらに、膵臓の消化酵素のかわりとなるような酵素剤をドッグフード・食事とともに与えることも有効です。
※犬の下痢嘔吐など消化器疾患の食事について、「犬の下痢嘔吐、治療と食事」で詳細をお伝えしています。
2.犬の高脂血・高血糖が関わる病気

このところ、高脂血・高血糖が関わる犬の病気が、どんどん増えています。犬の高脂血・高血糖が増えている理由は、ワンちゃんの運動不足とともに、ドッグフードの問題が大きいと考えられています。
犬の膵炎
犬の膵炎は、ドッグフード・食事の中の「脂肪」と深く関係しています。実際に、コレステロールや中性脂肪の血中値が高いことが多く、高脂血対策が必要となります。
膵炎の犬の90%で嘔吐がみられ、腹痛・食欲不振・元気がない・下痢・発熱などの症状が特徴です。膵炎の原因として、悪質な高脂肪ドッグフードやアンバランスな食事・おやつ、薬害、肥満、その他の病気などが挙げられます。
犬の膵炎は、適切な治療・食事対策をせずに放置しておくと、死亡につながる怖い病気です。特に、急性膵炎を発症した場合、治療が遅れれば遅れるほど、死亡率が高まります。また、治療により急性膵炎が完治したとしても、再発や慢性膵炎に移行することもよくあり、予後の食事管理も重要です。
犬の膵炎の食事対策として、「脱水対策」「適度なタンパク質(高タンパクだが多すぎもNG)」「低脂肪」が重要ポイントです。つまり、食事とともにたっぷりと水を与え、15~30%のタンパク質、15%以下の脂肪が望まれます。膵炎とともに肥満や高脂血を抱える犬の場合、脂肪を10%以下にすることが好ましいです。
※犬の膵炎について、「犬の膵炎 治療と食事」で詳細をご案内しています。
犬の糖尿病
犬の糖尿病は、増加傾向にあります。もともと、犬の糖尿病は遺伝的な要因も大きいですが、それ以上にアンバランスな食事やおやつ・運動不足などが原因となるケースが増えています。
高血糖という検査結果のほか、多飲多尿・よく食べるのに痩せる(逆に肥満から糖尿病が発症するケースもあり)といった犬の症状がみられれば、糖尿病を疑うべきかもしれません。さらに末期に近い糖尿病では、嘔吐・元気の喪失・口臭などもみられるようになります。また、膵炎やクッシング症候群などの併発や白内障がみられることも多く、健康的な余命をおくるためには、糖尿病以外の併発疾患へのケアも大切です。
犬の糖尿病の治療・対策は、おもに「インスリン」と「食事」です。インスリンは、基本的に生涯続けることになり、相応の治療費用もかかってきます。
犬の糖尿病について、食事対策の重要ポイントは、やはり「糖質制限」です。消化されやすく血糖値上昇につながりやすい糖質をさけつつ、食物繊維を増量したドッグフード・食事が好ましいです。加えて、脂肪量を少なめにし、タンパク質をしっかりとれる内容が望まれます。ただし、糖尿病と併発しやすい腎臓疾患(腎不全)を抱えている犬は、低タンパク質が条件になります。そして、膵炎と同じく水をたっぷり与えるうようにしましょう。
※犬の糖尿病についての詳細は、「犬の糖尿病 治療と食事」をご覧ください。
犬の高脂血症・脂質代謝異常症
高血糖とともに、コレステロール値や中性脂肪値が高い状態(高脂血)の犬も増えています。こういった高脂血症・脂質代謝異常症の原因は、高脂肪などの食事によるところが大きいです。症状がわかりにくく、血液検査で発覚したり、膵炎などを伴う嘔吐・食欲不振、神経障害を伴う発作により、高脂血症とわかることもしばしばです。
犬の高脂血症の治療薬もありますが、まずは食事対策を実施することが一般的です。
食事の絶対的な条件は、「低脂肪」。そして、他の病気の有無などを見ながら、糖質やタンパク質などに留意したドッグフード・食事が推奨されるケースもあります。
また、最近では「腸内環境」の大切さが理解されつつあります。高脂血症と善玉菌・悪玉菌のバランスには関係性があり、善玉菌を増やすような食事・ドッグフードも大切と考えられます。
※犬の高脂血症の詳細は、「犬の高脂血症 治療と食事」にてご紹介しています。
犬のクッシング症候群
クッシング症候群という病気は認知度が低く、血液検査により、自分の愛犬が発症してはじめて知るというケースがほとんどです。でも、クッシング症候群の犬は年々増加しています。
犬のクッシング症候群では、多飲多尿・異常な食欲・痩せているのにお腹だけ膨れている・脱毛などの症状がみられます。副腎ホルモン(コルチゾールなど)の過剰分泌による病気であり、脳下垂体や副腎に腫瘍ができることが直接の原因と考えられています。そのため、一種の腫瘍性疾患とみることもできます。
異常に分泌しているホルモンをコントロールする薬の投与が、クッシング症候群の基本的な治療方法です。治療薬の量をコントロールできれば、健康的な余命をおくることができますし、寿命を全うすることも可能です。
また、治療薬に加えて、犬のクッシング症候群ならではの代謝トラブルに対応した食事療法も要・検討です。クッシング症候群の犬は、「高脂血」「高血糖」「タンパク質不足」という栄養代謝トラブルを抱えがちです。そのため、「低脂肪」「低糖質」「高タンパク質」という食事・ドッグフードが望まれます。
※更に詳しい内容は、「犬のクッシング症候群 治療と食事」をご覧ください。
犬の甲状腺機能低下症
「甲状腺機能低下症」は、犬の甲状腺ホルモンの分泌不全がおこる病気です。脱毛・元気の喪失・むくみなどの症状がみられます。このところ検査方法が明瞭になり、犬にとても多い病気と理解されるようになりました。
犬の甲状腺機能低下症のはっきりとした原因は不明ですが、自己免疫疾患により甲状腺ホルモンの分泌組織がダメージを受けることや遺伝的な要因が想定されています。また、クッシング症候群が原因となることも多く、併発しやすい疾患となっています。
甲状腺ホルモンを投薬することが主な治療方法です。薬の量をうまく調整できれば、健康な犬と同じような生活をおくることが可能です。
また、薬と併せて、「低脂肪」「低糖質」「高タンパク質」の食事・ドッグフードも推奨されます。甲状腺機能低下症の犬は、ホルモン異常により高脂血・高血糖になりやすく、タンパク質が不足しがちであり、その栄養トラブルに対応した食事が望まれます。
※犬の甲状腺機能低下症の詳しい内容は、「犬の甲状腺機能低下症 治療と食事」でご案内しています。
犬のメタボ・肥満
肥満の犬は、様々な病気リスクを抱えており、寿命が短くなる傾向にあります。だから、肥満解消の正しいダイエットが必要です。
そんな中、2016年秋から、「犬のメタボ4基準」が施行されます。今まで曖昧だった「犬のメタボ」について、具体的な数値による目安チェック基準が導入されることになります。
- 「肥満」 → BCS 3.5以上
- 「高血糖」 → 血糖値120(mg/dl)以上
- 「高脂血」 → トリグリセリド(中性脂肪)165(mg/dl)以上、総コレステロール200(mg/dl)以上
- 「免疫力低下」 → アディポネクチン(免疫ホルモン)10(μg/ml)未満
肥満犬は、単なるダイエットだけでなく、これら4基準対策を全て実施することが望まれます。そして、犬の肥満・ダイエット対策の最重要ポイントは「食事」です。犬のメタボ4基準に対応した食事・ドッグフードにより、ダイエットを目指しましょう。
犬の肥満・メタボ対策の食事として、まずは「低糖質」「低脂肪」がポイントです。これにより、高血糖・高脂血の対策をとれることはもちろん、低カロリーな食事につながるため、自然なダイエットも実現可能です。
免疫力については、「腸の健康」や「タンパク質」が大切です。善玉菌を増やすような食事・ドッグフードにより、腸内環境を整えましょう。そして、タンパク質をしっかり補給し、基礎代謝アップとともに免疫力キープを心がけ、犬の肥満解消・ダイエットを実現しましょう。
※より詳しい犬のメタボ対策・健康ダイエットについて、「犬のダイエット 4つの食事対策」でお伝えしています。
3.犬のがん・腫瘍性疾患

犬のがん・腫瘍性疾患は、言うまでもなく、命に関わる怖い病気です。病種がとても多く、ざっと挙げるだけでも「乳腺腫瘍」「肥満細胞腫」「リンパ腫」「血管肉腫」「脳腫瘍」「肝臓がん」「皮膚がん」「メラノーマ」などがあります。悪性腫瘍であれば、余命宣告を受けることもしばしばです。
犬のがん・腫瘍は、症状も多岐にわたります。末期症状に近づくほど、元気や食欲を失うことなどが一般的です。原因は不明な病種がほとんどで、遺伝的要因・食事・ストレスなどが挙げられます。
犬のがん・腫瘍の治療方法は、主に「手術」「抗がん剤」「放射線治療」です。これらを組み合わせた治療もよく行われます。良性腫瘍・悪性腫瘍の見極めや転移・再発の有無、ステージ・進行度の判断など、検査により治療方針を決めることも大切なポイントです。また、犬のがん・腫瘍の治療では、国の保険がないこともあり、高額な治療費用がかかります。
そして、犬のがん・腫瘍に共通する食事療法も見逃せません。
がん・腫瘍の犬は、「腫瘍に糖質を奪われる」「犬自身はエネルギー不足になる」「活力・免疫力が低下する」といったトラブルを抱えています。これら栄養代謝トラブルに対応した内容が「犬のがん・腫瘍 食事療法」です。具体的には、「糖質制限」「高脂肪・高オメガ3脂肪酸」「高タンパク質・アルギニン」「免疫力キープ」を満たす食事・ドッグフードが望まれます。
※犬のがん・腫瘍について、詳細は「犬のがん・腫瘍 治療と食事」にてご紹介します。
4.犬の皮膚病・アレルギー
犬の皮膚病には、膿皮症・アトピー性皮膚炎・疥癬(カイセン)・外耳炎・マラセチア・アカラス・食物アレルギーなど、様々な病気があります。細菌・真菌(カビ)・寄生虫の感染、アレルギーなど、それぞれ原因や治療方法が異なるため、症状をしっかりチェックしなければなりません。中には犬同士はもちろん、人にうつる皮膚病もありますし、注意が必要です。
犬の皮膚病の症状チェック方法として、動物病院での診断はもちろん、赤い湿疹やできもの・斑点、黒いかさぶたやフケなど色や形状、臭いや痒がり方などで推測することも大切です。場合によっては、皮膚炎と皮膚がんの見分けがつきにくいケースもあります。
犬の皮膚病の対策には、ステロイドなどの薬による治療、シャンプーや薬浴による衛生管理、そして食事・ドッグフード対策があります。
犬の皮膚病すべてに共通する食事対策の内容として、「オメガ3脂肪酸」「皮膚バリア機能のキープ」「栄養バランス」「免疫バランスの維持」といったところがポイントとなります。
※犬の皮膚病について、詳細を「犬の皮膚病 治療と食事」にまとめています。また、皮膚病に関わる「犬の食物アレルギー対策」も併せてチェックいただければと思います。
5.犬の心臓病
犬の心臓病には、心雑音や不整脈をはじめ軽度なものから、僧帽弁閉鎖不全症・心筋症・フィラリアなどの病気、重度の心不全にいたるまで、多岐にわたります。心臓病の犬に特徴的な症状として、「運動をしたがらない」「失神」「咳」「呼吸が苦しそう」などが挙げられます。これらの症状が続くようであれば、心臓病の可能性が考えられます。
原因は、遺伝的な要因・ストレス・食事の乱れ・肥満・フィラリア感染などが考えられます。
犬の心臓病の治療として、薬の投与・安静療法・食事療法の3つが挙げられます。薬は、体内の水分・塩分を排出するタイプのものが一般的です。犬の心臓病は、脈拍や心音の検査により、初期症状でみつかりやすい傾向にあります。だからといって、副作用リスクのある薬に頼りすぎないようにしましょう。
また、安静にすることも犬の心臓病では大切な治療方法です。過度な運動はさけるようにしましょう。
そして、食事療法も大切です。特に、塩分(ナトリウム・クロール・リン・カリウム・マグネシウム)の適量制限とタウリン・L-カルニチンの欠乏を避ける食事・ドッグフードが必要です。さらに、犬の心臓病が重症度によっても、適切な栄養内容が異なります。心臓病が重症になればなるほど、食事・ドッグフードの塩分制限などが厳しくなります。
6.犬の腎臓病
腎臓病は、犬の死亡原因3位の病気とされています。腎不全や尿毒症など、とても怖い病気です。多飲多尿、無臭の尿、食欲不振、嘔吐、痩せる、貧血、高血圧、元気の喪失などの症状がみられます。
腎臓は、身体の老廃物などをろ過する機能をもっています。ろ過を行う「ネフロン」という構造が目詰まりをおこし、腎臓病の発症原因となることが多いです。犬の腎臓病の根本的な原因として、食事の乱れ・ストレス・老化・遺伝性・感染・自己免疫疾患・薬害などが挙げられます。
血液検査による血清クレアチニン濃度により、犬の腎臓病のステージ(進行度)が決まり、治療方法が検討されます。そして、腎臓病は完治が難しい病気です。そのため、輸液・点滴・薬などの対処療法と食事療法をくみあわせ、症状進行を緩和することが大切です。
犬の腎臓病の食事療法には、複数のポイントがあります。「水をしっかり与える」「低タンパク質」「塩分制限(ナトリウム・クロール・カリウム・リン)」「オメガ3脂肪酸」「ビタミンE・ビタミンC」が挙げられます。これらの条件をみたす、食事療法食・ドッグフードを与えることが重要です。
7.犬の尿結石
犬の尿結石には、主に「ストルバイト結石」「シュウ酸カルシウム結石」の2つがあります。
犬のストルバイト結石の食事・ドッグフードの条件として、「タンパク質の制限」「リン・マグネシウムの制限」「尿の酸性化」「十分な水分補給」が挙げられます。また、ストルバイト結石発症時の「治療用」と「予後管理用」で最適な食事内容も変わってきます。
対して、シュウ酸カルシウム結石は、ストルバイト結石と食事対策が真逆な点があります。「タンパク質の制限」「カルシウム・ナトリウム・マグネシウム・リンの制限」「シュウ酸を含む食品をさける」「ビタミンCを避ける」「尿のアルカリ化」が食事療法のポイントです。
かつては、犬の尿結石といえば、「ストルバイト結石」が大多数を占めていました。しかし、このところ「シュウ酸カルシウム結石」の犬も増えており、人間との共生が進んだ結果、野菜などシュウ酸食品をとりすぎていることなどが原因として考えられます。
また、「ストルバイト結石」と「シュウ酸カルシウム結石」の両方を発症している犬も多くみられます。この場合、尿のpH条件が真逆になることから、完璧な対策が難しくなります。基本的には、ストルバイト結石よりの食事対策を施すことになります。
8.犬の脳神経系疾患
てんかん・水頭症・脳梗塞・うつ病・認知症など、犬の脳神経系疾患は、多岐にわたります。高齢犬になるにつれ、脳神経の病気への発症率が高まり、性格が変わったり徘徊や無駄吠えなどの症状により、飼い主さんは大変な苦労をされています。
これらの病気に共通する点として、「認知機能の弱まり」があります。そのため、犬の脳神経系疾患の食事対策では、認知機能をケアすることがポイントとなります。
そして、犬の認知機能ケアの食事対策は、「抗酸化力」というキーワードがポイントです。具体的には、ビタミンE・ビタミンC・セレニウム・L-カルニチン・α-リポ酸・オメガ3脂肪酸・野菜や果物など、抗酸化力を有する成分・原材料をたっぷり活用した食事・ドッグフードが望まれます。
9.犬の肝臓・胆のう疾患
犬の肝臓や胆のうは、様々な代謝機能をになう、とても活発な臓器です。そのため、肝臓病や胆のう疾患の犬は、複雑な栄養代謝トラブルを抱えることになります。
犬の肝臓病は、初期症状がわかりにくく、発見したときには肝不全の末期状態であることもよくあります。肝不全になると、黄疸や腹水などの症状があらわれてきます。
犬の肝臓病の原因として、アンバランスな食事・悪質な原料や添加物・緑黄色野菜のとりすぎ・ストレス・薬害・化学物質の摂食・ウィルスや細菌の感染などが挙げられます。
投薬治療とともに、食事療法も重要なポイントです。「高カロリー」「タンパク質の制限」「アルギニン・タウリンの摂取」「ナトリウム・銅・鉄の制限」「亜鉛の摂取」「ビタミンE・ビタミンCの摂取」など、犬の肝臓病の食事療法として挙げられます。
犬の病気 食事療法のまとめ
- 食事療法として、犬の各病気ごとに対応した栄養内容のドッグフードを与えることが大切。
- 下痢嘔吐など消化器疾患の犬には、「高消化性」「高栄養」「食物繊維バランス」「ミネラル補給」「善玉菌アップ」の食事を与える。
- がん・腫瘍性疾患の犬には、「低炭水化物」「高脂肪(高オメガ3脂肪酸)」「高タンパク質(高アルギニン)」「」免疫力維持の食事療法がポイント。
- 高脂血・高血糖の病気を抱える犬は、お互いの病気が併発しやすく、「低脂肪」「低糖質」「タンパク質などの補給」「腸の健康(免疫力維持)」の4ポイントを兼ね備えたドッグフードが望ましい。
- 心臓病の犬には、「塩分制限」「タウリン・L-カルニチンの補給」の食事療法が必要。
- 犬の腎臓病では、「水をしっかり与える」「低タンパク質」「塩分制限(ナトリウム・クロール・カリウム・リン)」「オメガ3脂肪酸」「ビタミンE・ビタミンC」という食事療法が望まれる。
- 犬の尿結石には、主に「ストルバイト結石」「シュウ酸カルシウム結石」の2種があり、それぞれ異なる食事対策が必要。
- 犬の脳神経系疾患では、「認知機能ケア」を実現するために、食事・ドッグフードは「抗酸化力」にこだわることがポイント。
- 肝臓病の犬は、「高カロリー」「タンパク質の制限」「アルギニン・タウリンの摂取」「ナトリウム・銅・鉄の制限」「亜鉛の摂取」「ビタミンE・ビタミンCの摂取」の食事・ドッグフードが望まれる。