犬の下痢には、大きく分けて4つのタイプがあります。
「吸収不良タイプ」「腸粘膜の崩壊タイプ」「胃腸の運動性不調タイプ」「水分の異常分泌タイプ」の4つです。
犬の下痢がこれら4つのうち、どのタイプに属するのかを見極めることは大切です。なぜなら、4つの下痢タイプごとに、犬の症状・原因・治療方法・食事対策が異なるためです。
このページでは、犬にみられる下痢の4タイプについて、症状・原因と治療方法・食事対策をご案内します。
<目次>
犬の4つの下痢タイプ、見分け方
「犬の下痢」と言っても、その原因や細かい症状は様々です。そして、個々の下痢症状によって、治療方法や食事対策も異なります。
犬の生理学の観点からは、「吸収不良タイプ」「腸粘膜の崩壊タイプ」「胃腸の運動性不調タイプ」「水分の異常分泌タイプ」という4つの下痢タイプに分類することができます。そして、犬の4つの下痢タイプごとに、治療・食事療法を検討することが大切です。
そのため、まずは「愛犬の下痢はどのタイプなのか?」を理解することが対策の第一歩となります。
1)「吸収不良タイプ」の下痢
犬の下痢でもっとも多いのが「吸収不良タイプ」です。犬の腸内に吸収できない栄養があり、下痢につながってしまいます。「浸透圧性下痢」と呼ばれることもあります。
「吸収不良タイプ・下痢」の原因
消化不良・吸収不良、浸透圧緩下剤の投与、食べすぎ、などが原因となります。
「吸収不良タイプ・下痢」の症状(見分け方)
多量の水や軟便を排泄することが特徴的な症状です。また、犬が脂肪源の消化不良であった場合、脂っぽい「脂肪便」の下痢を多量に出すこともあります。
2)「腸粘膜の崩壊タイプ」の下痢
犬の下痢で2番目に多いものが「腸粘膜の崩壊タイプ」です。
犬の腸の表面には、腸内環境と器官を隔てる「粘膜」というバリアが存在します。この「腸・粘膜」のおかげで、犬の腸は傷つくことなく消化吸収&排泄をスムーズに進めることができます。
ところが、「腸・粘膜」のバリア機能の一部が崩壊してしまうことがあります。そして、粘膜の崩壊がおこると、犬の下痢につながってしまいます。「滲出性下痢」と呼ばれることもあります。
「腸粘膜の崩壊タイプ・下痢」の原因
犬の「腸粘膜の崩壊タイプ」下痢は、食中毒や炎症性の腸疾患などが原因となります。
「腸粘膜の崩壊タイプ・下痢」の症状(見分け方)
腸粘膜の崩壊により、血液や粘液・細胞内の液体が腸内にしみ出てきます。そして、犬の便中の水分が増えてしまい、水状もしくは泥状の下痢となることが「腸粘膜崩壊タイプ」の症状です。
また、下痢の頻度が多く、中には黒色タール状の血便となるケースもあります。
さらに、腸粘膜崩壊タイプ・下痢の犬は、「タンパク喪出性腸症」と呼ばれる腸疾患を発症することもあります。「タンパク喪出性腸症」の犬は、タンパク質が腸内に漏れ出てしまう状態にあり、低タンパク血症・低アルブミン血症にもなりがちです。「タンパク喪出性腸症」の犬では、下痢とともに鮮血や黒色タール便が症状としてみられることもあります。
3)「胃腸の運動性不調タイプ」の下痢
胃腸、特に犬の腸の運動性が不調となり、下痢がおこることもあります。
腸は「ぜん動運動」と呼ばれる動きにより、排便を促します。ところが、何らかの原因により「ぜん動運動」が異常に活発化することがあり、それに伴って腸の内容物が急速に排泄されることになり、犬が下痢を起こすことになります。
また、犬では「ぜん動運動」が減少する「腸閉塞」という病気になることもあり、こちらも腸運動性の不調による下痢症状をまねきます。
「胃腸の運動性不調タイプ・下痢」の原因
ぜん動運動の高まりにより、腸内容物が速く移動することになれば、水分も十分に吸収されないまま下痢・軟便となってしまいます。
その根本的な原因として、犬が抱える「ストレス」と「腸内細菌バランスの乱れ」などが挙げられます。
ストレスを抱える犬は、ミネラルの消費が激しくなります。すると、ミネラルバランスが崩れてしまいます。ミネラルバランスが崩れると、犬の腸内の善玉菌が減り、悪玉菌が優勢となってきます。そして、悪玉菌を追い出そうとする力が働き、犬の腸が異常なぜん動運動をとるようになるのです。
このような「ストレス」→「ミネラルバランスの崩れ」→「腸内細菌バランスの乱れ」→「腸のぜん動運動の異常」→「下痢」という症状は、「過敏性腸症候群」という病名がつくこともあります。
「胃腸の運動性不調タイプ・下痢」の症状(見分け方)
胃腸の運動性不調タイプの下痢は、排便後もぜん動運動がおさまらず、腹痛やお腹の違和感が残りがちです。そのため、犬が下痢・軟便をしたあとに、排便されないのに出そうとしていたり、お腹を痛そうする素振りなどの症状がみられれば、「胃腸の運動性不調タイプ」が疑われます。
4)「水分の異常分泌タイプ」の下痢
「水分の異常分泌タイプ」の下痢は、犬の消化器粘膜から、水分と塩分が異常に分泌されることで起こります。人では「コレラ」などの感染によりしばしば重篤な症状ががみられますが、犬ではあまり発症しないタイプの下痢です。
「水分の異常分泌タイプ・下痢」の原因
犬が細菌やウィルス・寄生虫に感染し、それら外敵が産生する毒素が原因となり、腸内で水分・塩分の異常分泌がおこって下痢が引き起こされます。
「水分の異常分泌タイプ・下痢」の症状(見分け方)
このタイプの特徴的な症状は、多量の液状便・水下痢です。そして、犬が脱水症状におちいることもあり、注意が必要です。
犬の4つの下痢タイプ、治療方法・食事対策

ワンちゃんの下痢が4つのタイプいずれに属するのか、見当がつけば、いよいよ治療方法・食事対策のチェックです。
犬の4つの下痢タイプごとに、対策をみていきましょう。
1)「吸収不良タイプ」の治療方法・食事対策
犬に最もよくみられる「吸収不良タイプ」の下痢について、基本の治療方法・食事対策は「絶食」です。通常、24~36時間の絶食により、犬の下痢症状が改善されます。
絶食により、下痢からの回復がみられれば、犬の腸に合った食事をとることがポイントとなります。
(※犬の腸に合った食事について、詳細は「犬の下痢嘔吐 治療と食事」をご参照ください。)
(※犬の絶食については、次のページもご覧ください。→「犬の下痢、絶食のポイント」)
2)「腸粘膜の崩壊タイプ」の治療方法・食事対策
タンパク喪出性腸症や腸リンパ拡張症を含む、犬の「腸粘膜の崩壊タイプ」の下痢では、絶食や食事量の制限だけでは対処できないことが一般的です。
また、食中毒が原因であれば、下痢止めを活用した治療も禁物です。犬の下痢は、悪いものを排出する反応でもあるため、不適切な下痢止めは体内に毒素をためこんでしまい、症状悪化の恐れがあるためです。
食事対策については、「高栄養・高消化食」の方が良い場合と「高繊維食」が適しているケース、があります。これは、犬の腸粘膜の崩壊している部位などによって、最適な食事が異なります。
(※犬の下痢対策の「高栄養・高消化食」「高繊維食」については、「犬の下痢嘔吐 治療と食事」をご参照ください。)
3)「胃腸の運動性不調タイプ」の治療方法・食事対策
腸の運動性が不調になっている犬の場合、腸内の悪玉菌が異常に繁殖しているケースが多いです。
対策として、抗生物質などの薬による治療もありますが、腸内細菌が増えることをおさえるために、悪玉菌のエサとなる食事残渣を減らさなければなりません。そのため、消化率が高い食事・ドッグフードを与えることが重要ポイントとなります。消化率が高い食事は、犬の体内に吸収されやすいため、残渣が腸内に残りにくくなります。それにより、腸内悪玉菌をコントロールすることが狙いです。
また、「オリゴ糖」を犬に与えることも有用です。オリゴ糖は、善玉菌のエサとなるが悪玉菌には利用されにくい、という特徴があるため、犬にとって良い腸内細菌のみを増やしてくれます。
(※犬の腸内乳酸菌を増やす方法について、「犬への乳酸菌効果を高めるコツ」をご参照ください。)
4)「水分の異常分泌タイプ」の治療方法・食事対策
水分の異常分泌タイプの下痢では、犬が絶食してもあまり症状は好転しません。そして、多量の水下痢を伴うため、適切なバランスのミネラルと水分を補給することが大切です。
そして、感染菌・ウィルス・寄生虫に対する適切な治療も必要となります。
食事対策としては、脱水対策とともに、下痢の状態をみきめながら犬の腸に負担が少ないタイプの栄養補給が望まれます。
まとめ
- 犬の下痢には、「吸収不良タイプ」「腸粘膜の崩壊タイプ」「胃腸の運動性不調タイプ」「水分の異常分泌タイプ」の4つがある。
- 犬の下痢・4つのタイプは、症状によりある程度の見極めが可能。そして、4つの下痢タイプごとの治療・食事対策が望まれる。
- 「吸収不良タイプ」の下痢は、絶食が対策の基本。「腸粘膜の崩壊タイプ」では下痢止めは禁物で、犬の症状に応じた食事対策がポイント。「胃腸の運動性不調タイプ」は、犬にとっての消化性を高め、オリゴ糖などを与える。「水分の異常分泌タイプ」は、感染菌・ウィルス・寄生虫への治療とともに、脱水症状のケアと犬の下痢症状を見極めながら腸に負担が少ない栄養を補給する。
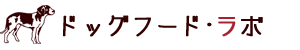










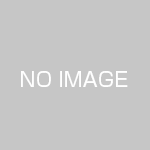





































































この記事へのコメントはありません。