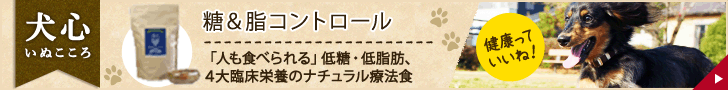ホルモン異常の内分泌疾患として知られる、犬のクッシング症候群。ワンちゃんにとても多い病気です。副腎という器官でのホルモンが異常に分泌されるようになり、副腎皮質機能亢進症とも呼ばれています。
犬のクッシング症候群では、多飲多尿・脱毛などの症状とともに、身体の内側では代謝障害が生じます。そして、薬を原因とする「医原性タイプ」と「自然発生タイプ」、2種のクッシング症候群が知られています。
これら2種のタイプに合わせながら、副腎のホルモン分泌をコントロールする薬を投与することが、一般的な治療方法です。そして、あまり知られていないものの、クッシング症候群特有の代謝異常に対応した、食事療法も存在します。そのため、治療薬と食事療法を合わせて検討することが望まれます。
このページでは、犬のクッシング症候群の症状・原因・検査にふれながら、治療方法・食事対策をご案内します。記事をとおして、クッシング症候群のワンちゃん達が寿命を全うできるようなサポートができれば幸いです。
<目次>
- 犬のクッシング症候群、症状&2タイプの原因
- クッシング症候群の検査方法
- 治療薬・手術について
- 食事療法4つのポイント
- 食事療法の実践
- クッシング症候群と併発しやすい病気について
- 犬のクッシング症候群、対策のまとめ
犬のクッシング症候群、症状&2タイプの原因
クッシング症候群とは、「コルチゾールなどの副腎皮質ホルモン」が異常分泌される、犬で頻発する病気です。
クッシング症候群、よく見られる症状
- 多飲多尿
- よく食べる(常に空腹状態のケースもある)
- お腹がふくれる(脂肪の移動に伴う体形の変化)
- 脱毛(銅の部分などで左右対称に毛が抜ける)
- 皮膚が薄くなる、皮膚病を発症する
- 筋力が落ちる
- 散歩・運動時に呼吸が激しくなりやすい(すぐにハアハアする)
犬のクッシング症候群、2タイプの原因
通常、脳の視床下部・下垂体からの指令を受け、コルチゾールなど副腎皮質ホルモンは適切に分泌されます。適切なコルチゾール分泌は、犬の食欲や元気を増し、消化器系をはじめとする健康状態を整え、さらには身体をストレスに対応できる状態にします。
ところが、クッシング症候群の犬では、副腎で作られる「コルチゾール」などのホルモンが過剰に分泌されてしまいます。常にコルチゾールが出すぎるクッシング症候群は、犬に大きな負担を及ぼします。
犬のクッシング症候群の原因は、投薬に伴う「医原性タイプ」と「自然発生タイプ」の2種があります。原因に基づく2タイプのクッシング症候群は、それぞれ治療方法も異なる点があるため、区別して考慮することが大切です。
医原性タイプ・クッシング症候群
ステロイドなどのグルココルチコイドの長期投薬により、発症するクッシング症候群です。犬では、特にグルココルチコイドに対する耐性がないため、医原性クッシング症候群がよく見られます。
犬にとって生理的な許容範囲を超えたグルココルチコイドを投薬され続けると、脳下垂体は副腎ホルモンにブレーキをかける状態となり、副腎皮質は委縮します。ところが、体内には投薬されたグルココルチコイドが存在するため、食欲があり、異常徴候が見られず、副腎自体が委縮していることに気づきにくいところがあります。
治療すべき病気の状態にもよりますが、例えば高用量のプレドニゾロンを長期投与することは好ましくありません。また、ステロイド入りの外耳炎治療薬なども、犬の医原性クッシング症候群の原因となりやすく、過剰投与は避けなければなりません。
自然発生タイプ・クッシング症候群
「自然発生タイプ」のクッシング症候群は、犬種が関係している可能性があります。好発犬種として、プードル、ダックスフンド、ビーグル、ボストンテリア、ボクサーが知られています。
犬の自然発生・クッシング症候群の原因は、約85%が脳下垂体の腫瘍、約15%が副腎腫瘍と見なされています。これらは良性腫瘍であることが一般的ですが、副腎ホルモンの異常分泌を促す、もしくはホルモン制御系が不全になることにより、クッシング症候群を発症させます。
クッシング症候群の検査方法
犬のクッシング症候群は、確定診断となるまでに幾つかの検査ステップを踏むことが一般的です。下記、確定診断にいたる検査ステップの例をご紹介します。
ステップ1)身体検査
犬にクッシング症候群ならではの症状、「多食」「多飲多尿」「お腹の膨らみ・脂肪の移動」「筋力低下」「左右対称性の脱毛・皮膚の変化」「呼吸異常」などが無いか、チェックします。
ステップ2)血液検査
CBCと呼ばれる「血球数検査」と肝臓値などの「血液化学検査」を行います。
まず、犬のクッシング症候群のCBCでは、下記のような傾向が見られます。
- 赤血球:男の子では正常、女の子では正常かやや増加
- 総白血球:正常かやや増加
- 成熟好中球:増加
- リンパ球:減少
- 単球:増加
- 好酸球:減少
血液化学検査では、下記がチェックポイントになります。
- ALTの増加が見られることがある(ステロイド肝障害による肝腫大などが原因)
- ALPが増加するケースが多い、GGTの上昇もしばしば見られる
- 高コレステロール(TCho)も頻発する
なお、高コレステロールなどから、糖尿病・胆汁うっ滞・甲状腺機能低下症などとクッシング症候群が誤診されるケースもよくあります。特に、犬の甲状腺機能低下症は、クッシング症候群と所見が似通っています。中には、甲状腺機能低下症を判別する検査項目である「T4」が、クッシング症候群でも低値を示すこともあり、鑑別を困難にしています。(※クッシング症候群と甲状腺機能低下症を併発していることもしばしばです。)
(※甲状腺機能低下症について、詳しくは「犬の甲状腺機能低下症 治療と食事」をご覧ください。)
ステップ3)尿検査・X線検査
犬のクッシング症候群では、尿検査の「尿比重」に低下が見られます。また、クッシング症候群の犬の約50%で尿路感染が認められる、という報告もなされています。
そして、腹部X線検査により、腹腔脂肪の増加による「腹囲増大」「肝腫大」が多くの症例で見られます。また、副腎腫瘍が原因となっているケースでは、副腎の石灰化などが確認されることもあります。
ステップ4)特殊検査
「医原性」「自然発生」の鑑別、自然発生クッシングの確定、クッシングの原因(脳下垂体・副腎腫瘍)チェックなどを目的に、より特殊な検査が行われることもあります。
様々な方法が知られていますが、基本的にはある特定の条件下でコルチゾール測定を行う検査を実施します。
治療薬・手術について

犬のクッシング症候群では、「治療した方が未治療よりも生存期間が延長する」という確かなエビデンスが得られていません。そして、クッシングの治療行為は根治のためではなく症状を抑えるための対処療法になります。
それでも、クッシング症候群の治療は、実施した方がより良いと考えられています。(※犬に食欲不振が見られる場合は、クッシングの治療から入るべきではないとされています。なぜなら、クッシングの治療により、犬は必ず食欲が落ちてくるためです。)
まず、治療にあたり「医原性」「自然発生」どちらのタイプのクッシング症候群なのか、見極めることが重要です。もし「医原性」であれば、クッシング症候群の発症原因である薬の使用・用量を見直すことが第一の対策となります。
犬が「自然発生」タイプのクッシング症候群であれば、下記のような治療方法が検討されます。
治療薬
犬のクッシング症候群の治療薬として、「アドレスタン(トリロスタン、デソパン)」「o,p’-DDD」「ケトコナゾール」などが挙げられます。これら治療薬を順にご案内します。
アドレスタン(トリロスタン、デソパン)
犬のクッシング症候群では、比較的新しい治療薬として「トリロスタン」が使われるようになってきます。こちらは、「アドレスタン(共立製薬)」「デソパン(持田製薬)」などの商品名で取り扱われています。(これらの中で、「アドレスタン」が犬のクッシング症候群で使われることが多いため、以下、「アドレスタン」という表記でご案内します。)
※アドレスタンの副作用・留意事項
アドレスタン(トリロスタン)については、近年、様々な研究が報告されています。その中で、重要な知見は、「クッシング症候群の犬にアドレスタンを過剰量与えすぎない」という点です。過剰なアドレスタンは、副作用として副腎の機能不全・壊死を招くこと知られ始めており、特に治療当初は低用量からスタートしなければなりません。アドレスタン投薬開始から約10日間で効果が現れ始めるため、10~14日後にテストをするなど、1~2ヶ月は慎重に適量をチェックする必要があります。
o,p’-DDD
犬のクッシング症候群への治療方法として、「o,p’-DDD」というお薬もあります。「o,p’-DDD」は、副腎を破壊する作用があり、高用量で一挙に使用し、犬の副腎を小さくします。(※「o,p’-DDD」は、人や猫のクッシングでは無効であり、犬に特有の治療法とされています。)
「o,p’-DDD」に伴う副腎の縮小により、犬の食欲・飲水量が正常化し、クッシング症状が緩和されれば成功です。
※o,p’-DDDの副作用・留意事項
一方で、o,p’-DDD療法には危険も伴います。副腎破壊が進みすぎると、犬にクッシングとは逆の「副腎皮質機能低下症(アジソン病)」が発症しうる、という副作用があります。
そのため、o,p’-DDD療法を実施するのであれば、家庭内でも食事量・飲水量・元気・嘔吐など、犬の症状を十分にチェックしなければなりません。
ケトコナゾール
犬のクッシングの治療選択肢として、「ケトコナゾール」が検討されるケースもあります。ケトコナゾールは、日本国内では未承認の抗真菌薬です。アドレスタンと似た作用を示し、クッシング症候群の犬で過剰分泌されるステロイドホルモン合成をブロックします。(※日本で任んかされている別の抗真菌薬、例えば「イトリコナゾール」には、クッシング症候群の治療作用がありません。)
※ケトコナゾールの副作用・留意事項
ケトコナゾールは、犬の肝臓などへの副作用があることが知られています。また、他の薬物と併用することにより、作用が増強することもあるため、投与にあたっては十分な注意が必要です。
クッシング症候群の治療薬の費用
以上のような「犬のクッシング症候群の投薬治療」の場合、1ヶ月あたりの治療費は数万円~10万円ほどかかることが一般的です。
手術
副腎腫瘍を原因とするクッシング症候群の場合、「外科手術」も選択肢の一つです。まず、胸部X線・肝超音波検査などにより、腫瘍に転移がないかをチェックし、犬の状態を見ながら手術の可能性を検討します。
そして、手術前に薬によって高コルチゾールをコントロールし、手術後は副腎皮質機能低下症(アジソン病)対策の治療が必要となります。
犬のクッシング症候群の「手術による治療費用」については、10万円以上かかることが一般的です。
食事療法4つのポイント
それでは、いよいよ「犬のクッシング症候群・食事療法」についてご案内します。クッシング症候群の栄養代謝トラブルである「高脂血・高血糖」をケアすること、不足しがちなタンパク質などの栄養を補給すること、免疫力維持に努めること、をベースとした4つのポイントが重要です。クッシング症候群の治療をしない、という判断をされる飼い主さんもいらっしゃいますが、せめて食事療法を実施し、少しでも犬の負担を減らすことが望まれます。
1)良質な低脂肪
第一のポイントは、「低脂肪」です。クッシング症候群の犬は、コルチゾール分泌過剰により、高脂血症を伴うことが多いです。コレステロールや中性脂肪値が高くなりがちです。そのため、食事・ドッグフードの脂肪量を低く抑えなければなりません。
さらに、「脂肪の質」にも留意が必要です。犬の高脂血をケアする「オメガ3脂肪酸」「トリグリセリド」などを中心とした配合が望まれます。
そして、「脂肪の酸化防止」も大切です。加熱や長期保管(長く空気にふれること)により、脂肪の酸化が進みます。酸化した脂肪は、犬の健康被害の素となり、炎症を増長させることなどが知られています。クッシング症候群にも悪影響を及ぼすことが明らかであるため、できるだけ酸化していない脂肪を与えることにも気をつけましょう。
2)血糖値コントロール
2つめのポイントは、「血糖値のコントロール」です。クッシング症候群の犬は、高血糖になりやすい状態にあります。実際に、糖尿病を併発している犬も多くいます。
血糖値をコントロールするために、まずは、糖質・消化しやすい炭水化物を少なくしなければなりません。特に、ブドウ糖や砂糖など甘い食品や、高・炭水化物のドッグフードは与えないようにしましょう。
次に、血糖値アップを緩和する「食物繊維」や「消化されにくい炭水化物」に目を向けます。これらの成分は、糖吸収をブロックしてくれるため、血糖値コントロールに貢献してくれます。ただし、食物繊維には注意が必要です。緑黄色野菜の繊維質などは、肉食性の強い犬にはやや固く、腸などに負担を与えます。だから、糖吸収されにくい玄米・大麦・イモ類などを適量与えることがポイントになります。
3)タンパク質の補給
クッシング症候群の犬は、代謝異常により、自分の身体のタンパク質を分解利用しようとします。そのため、脱毛・筋力低下などの症状が見られるようになります。言い換えると、慢性的なタンパク質不足といえるような状態です。
そのため、クッシング症候群の犬には、タンパク質を十分に与えてあげなければいけません。一方で、クッシング症候群は糖尿病を併発しやすく、タンパク質量が多すぎると、血中のアミノ酸濃度がアップし、腎臓などに負担をかける恐れがあります。だから、クッシング症候群ならではの適量のタンパク質を与えることがベストです。
4)免疫力キープ
4つめのポイントは、「免疫力のキープ」です。犬のクッシング症候群の根本原因は、腫瘍であることが多く、その対策が必要です。
犬の免疫力を維持するためには、サプリメントなどの活用もお勧めできますが、より重要視したいこととして、食事・ドッグフード全体から「腸の健康」を目指すことがあります。小腸には、免疫細胞の60%以上が集まっています。腸内の善玉菌をアップさせることで、免疫細胞が元気をキープできるのです。元気な免疫細胞は、血中をめぐってコレステロールや血糖を食べてくれることも知られています。つまり、腸の健康による免疫力キープにより、犬の高脂血・高血糖をケアすることもでき、クッシング症候群の食事管理につながるのです。
食事療法の実践

以上の食事療法4ポイントを実践するコツについても、ご紹介します。
手作り食の基本
犬のクッシング症候群・食事療法を、手作りで実践したい方もいらっしゃることと思います。その基本的なポイントについて、ご案内します。
まず、低脂肪の肉・魚をメインにすえましょう。鶏ササミ・胸肉やお魚、場合によっては鹿肉・馬肉などもお勧めです。軽く茹でてあげましょう。
肉・魚だけでは、高タンパク質・高脂肪に偏ってしまうため、玄米・大麦・イモ類などを混ぜます。このあたりの配合バランスは、ご愛犬の血糖値などによって変わってきます(高血糖であれば、穀物・イモを少なめにしましょう)。玄米・大麦は炊飯して、イモ類は茹でこぼして与えましょう。さらに言えば、少量の玄米粉とミックスしてあげるとより好ましいです(炊飯米よりも生米の方が、難消化性であり、適度な配合は血糖値対策・腸の健康によいためです)。
さらに、ワンちゃんの好みに合わせて、野菜などを少量トッピングしてもOKです。ただし、野菜の繊維質やβカロテンなどの成分は、多量に与えると犬に負担となるため、しっかりと茹でて茹で汁を捨て、少量のみを与えるようにしましょう。
市販ドッグフード・療法食について
犬のクッシング症候群に対応した、市販のドッグフードや療法食を活用する際のポイント・選び方もお伝えします。市販のドッグフードはもちろん、病気対応の療法食であっても、犬のクッシング症候群用のものはほとんど見られません。そのため、ご紹介した「食事療法4ポイント」に照らし合わせて、各商品をチェックする必要があります。
まず、粗脂肪と粗タンパク質をチェックしましょう。粗脂肪15%以下(できれば10%以下)、粗タンパク質20~35%(できれば25~30%)あたりが目安になります。(※ただし、腎臓・心臓・肝臓などに疾患を持つワンちゃんは、この範囲が適正とは限りません。)
次に、炭水化物・糖質の量も確認したいところですが、ペットフードでこれら成分は表示が義務化されていません。そのため、多くの市販ドッグフードでは、炭水化物・糖質をチェックできないのです。そう考えると、ある程度の糖質制限をしているドッグフード・療法食を選ぶことになります。
さらに、原材料を見てみましょう。保存料・添加物など、犬の健康にネガティブな原料が多いものは、避けましょう。できるだけ自然素材メインのものが好ましいです。場合によっては、飼い主さん自身が匂いをチェックし、試食してみて、問題ないか判断しましょう。
クッシング症候群と併発しやすい病気について
最後に、犬のクッシング症候群と併発しやすい病気についても触れておきます。合併症が見られる場合、クッシング症候群の治療だけではなく、併発疾患への対策も考慮しなければなりません。
肺血栓症
犬のクッシング症候群の併発疾患の中で、最も重篤な症状が「肺血栓症」です。肺血栓症では、激しい呼吸困難が見られ、緊急治療が必要となります。
高脂血症・膵炎
クッシング症候群の犬では、ホルモンバランスの乱れにより、脂肪代謝にトラブルが生じ、「高脂血症」(高コレステロール・高中性脂肪)が頻発します。さらに、感染も起こりやすくなるため「膵炎」を発症するリスクも高いです。そのため、クッシング症候群の犬では、食事中の「脂肪」に十分な留意が必要です。
(※犬の膵炎対策について、詳しくは「犬の膵炎 治療と食事」をご覧ください。)
糖尿病
クッシング症候群に伴う体内ステロイドの過剰により、高血糖が誘発され糖尿病リスクが高まります。また、元々、糖尿病の犬がクッシング症候群を発症することもあります。そのため、クッシング症候群でも、食事によるある程度の血糖値コントロールが望まれるところです。
(※犬の糖尿病については、「犬の糖尿病 治療と食事」で詳しくご案内しています。)
甲状腺機能低下症
犬のクッシング症候群と甲状腺機能低下症を併発するケースも非常に多いです。これらは一部の症状・血液検査データが似通っているところがあり、誤診につながることもあります。
(※甲状腺機能低下症に関して、次のページもご参照ください。→「犬の甲状腺機能低下症 治療と食事」
肝臓障害
クッシング症候群の犬では、血液検査でALT・ALP・GGTの数値上昇が見られがちです。これらは、肝臓機能の障害・肝臓病が疑われる数値項目ですが、中でもALT(GPT)が高値を示したときは、肝臓トラブルが疑われるところです。
ALT(GPT)が高い場合などは、クッシング症候群とともに肝臓への対処も検討しなければなりません。
(※肝臓病・肝臓トラブルについては、「犬の肝臓病、数値・症状に応じた治療&食事対策」で詳しくお伝えしています。)
高血圧
クッシング症候群の犬の約50%は、高血圧と言われています。高血圧は、腎臓病・心臓病・肺血栓症・眼の病気などにつながる恐れがあります。そのため、クッシング症候群の犬では、血圧測定が欠かせません。
高血圧の併発が見られた場合、通常はクッシング症候群の治療を優先させます。もし、クッシング症候群がコントロールできているのに高血圧が続く場合は、血圧を下げる治療を検討します。
神経系の異常
脳下垂体を発症原因とするクッシング症候群では、犬の神経系に異常が見られることもあります。ふらつき・ぐるぐる旋回する・食欲がない・行動異常などがあれば、神経系にトラブルが起きている可能性があります。
腎臓・尿路トラブル
高血圧が見られがちなクッシング症候群の犬では、腎臓に圧力がかかり腎不全リスクが高まります。また、クッシング症候群の犬には、シュウ酸カルシウム結石が多い傾向があり、クッシングではない犬と比べて10倍の発症リスクがあるという報告もあります。
犬のクッシング症候群、対策のまとめ
以上、犬のクッシング症候群についてご案内しました。クッシング症候群は、難治性の病気ですが、うまくコントロールしてあげれば寿命を全うすることも可能です。このページを見ていただくことにより、病態を正確に把握し、適切な治療・食事対策をとっていただくヒントになれれば幸いです。下記、記事内容のまとめです。ご不明な点など、お問い合わせくださいませ。
- クッシング症候群の犬では、多飲多尿や脱毛などの症状が見られる。
- 犬のクッシング症候群は、薬の副作用による「医原性」と「自然発生」の2タイプの発症原因がある。
- クッシング症候群の検査では、「身体検査」「血液検査」「尿検査およびX線検査」「特殊検査」という段階を踏むことが一般的。
- 「医原性クッシング症候群」の治療は、原因となる薬を見直すことが第一の選択。「自然発生クッシング症候群」では、治療薬・手術が検討される。
- 犬のクッシング症候群の治療薬として、「アドレスタン」「o,p’-DDD」「ケトコナゾール」が挙げられる。根治治療ではなく、対処療法が目的となる。また、いずれの治療薬も副作用に留意が必要。
- 副腎腫瘍を原因とするクッシング症候群では、外科手術も選択肢となる。
- 犬のクッシング症候群の食事療法として、「低脂肪」「血糖値コントロール」「タンパク質の適量補給」「免疫力キープ」が挙げられる。
- 手作り食は、脂身の少ない肉・魚をメインに、玄米・大麦・イモ類などを混ぜ、場合によっては少量の野菜類をそえる。
- 市販ドッグフード・療法食については、「犬のクッシング症候群・食事療法4ポイント」に照らし合わせ、成分量や原材料をチェックして選択する。
- 犬のクッシング症候群には、併発しやすい病気もある。クッシングと共に、合併症の治療・対策も考慮する。